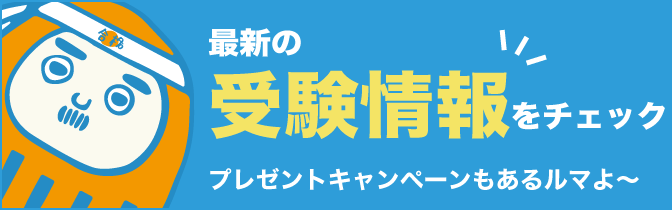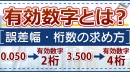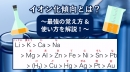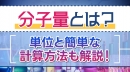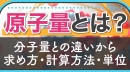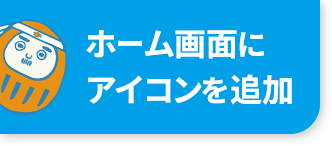組成式とは?書き方、分子式との違いや例題も解説!一覧表つき

「組成式の書き方がわからない……」という方や、「組成式と化学式・分子式との違いって何?」と思っている方も多いのではないでしょうか。
組成式を使うことで、構造元素の割合を、他の元素よりも簡単に書き表すことができます。化学分野を学ぶ上で、化学式や分子式を組成式で書き表すことができるようになれば元素の種類を覚えやすくなるでしょう。
本記事では、組成式の書き方をわかりやすく詳細に解説しています。例題を確認しながら、組成式の書き方をマスターしましょう。
・組成式とは何か分かる。
・組成式の使い方が分かる。
・化学式から組成式を書けるようになる!
【PR】勉強を効率的に継続して、志望校に合格したい方必見!

↓無料ダウンロードはこちら↓
【 目次 】
1.組成式とは?
2.組成式の書き方
①まずは陽イオン、陰イオンの種類を覚える
②種類を覚えたら左に陽イオン、右に陰イオンを書く
③陽イオン、陰イオンの比を求める
④求めた比を元素記号の右下に書く(比の値が1の場合は省略する)
組成式の書き方の例題:炭酸ナトリウム
3.組成式と分子式の違いとは?
4.覚えておきたい組成式の一覧表
1.組成式とは?
組成式とは、元素の種類と比を示す式です。
化学式には分子式、示性式、構造式、イオン式、電子式などさまざまな種類があり、組成式も化学式の一種です。構成元素の割合を最も簡単な整数比で表しています。
実際に例をみると分かりやすいです。
例えばC4H8O2という化学式で表される物質があったとします。
炭素と水素と酸素の数の比は2:4:1で、これを組成式にするとC2H4Oとなります。
化学式と組成式が同一の場合もあります。
C5H12Oという化学式の物質の場合は炭素と水素と酸素の数の比は5:12:1となり、組成式もC5H12Oとなるため、化学式と組成式は同一になります。
物質に含まれている元素の数と、それらの比が一致するときには、化学式と組成式が同じになるのです。
今まで混乱していたのは、化学式と組成式が同じ場合があるためかもしれませんね。
組成式と分子式の違いは、後で解説します。
2.組成式の書き方
組成式を書く場合は、以下の①〜④の順番で進めると簡単に求めることができます。
①陽イオン・陰イオンの種類を覚える
②左に陽イオン、右に陰イオンを書く
③陽イオン、陰イオンの組成比を求める
④求めた比を元素記号の右下に書く(比の値が1の場合は省略する)
手順をひとつずつ詳しく見ていきましょう。
①まずは陽イオン、陰イオンの種類を覚える
組成式の問題で、塩化ナトリウムなどの無機物を扱うときには、化学式を与えられず、組成式を物質の名称から答えなければならない場合もあります。
よく用いられる陽イオンと陰イオンの一覧表を作って覚え、組み合わせ方を理解しておけば簡単に問題を解けるようになるでしょう。
よく登場するイオンとしては、次のようなものがあります。
陽イオン…Li+、Na+、K+、NH4+、Mg2+、Ca2+など陰イオン…F–、Cl–、Br–、CH3COO–、OH–、SO42-、CO32-、PO42-、O2–など
②種類を覚えたら左に陽イオン、右に陰イオンを書く
例えば、塩化ナトリウムであれば、Na+Cl–という順になります。
③陽イオン、陰イオンの比を求める
ナトリウムイオンと塩化物イオンを組み合わせると塩化ナトリウムができます。この場合は陽イオンと陰イオンの比率が1:1になります。この比率のことを「組成比」といいます。
組成式を書く際には、この組成比を求める必要があります。
例えば、リチウムイオンと炭酸イオンを組み合わせると炭酸リチウムができますが、この場合組成比は1:1ではありません。
重要なのは、どのような比率で組み合わせると組成式を導き出せるかどうかです。
陽イオンは正電荷を帯びているのに対し、陰イオンは負電荷を持っています。
プラスとマイナスが互いに引き寄せ合う力を利用して物質が形成されていて、全体として電荷を帯びていない状態になっているのが特徴です。
そのため、陽イオンと陰イオンを組み合わせるときには、陽イオンの正電荷と陰イオンの負電荷が中和されるように、それぞれの数を選べばよいと言えます。
例えば塩化ナトリウムの場合には、ナトリウムイオンが+1の電荷を持ち、塩化物イオンは-1の電荷を持っています。よって、この2つを1:1の比率で組み合わせれば電荷が中和されるとわかるでしょう。
一方、炭酸リチウムの場合にはリチウムイオンは+1の電荷なのに対し、炭酸イオンは-2の電荷を持っているので、組成比は2:1になります。
④求めた比を元素記号の右下に書く(比の値が1の場合は省略する)
最後に、求めた比の値を、それぞれの元素記号の右下に書きます。比の値が1になる場合は、省略しましょう。
先ほどの炭酸リチウムの場合、組成比が2:1になるので、元素記号の右下に比を書いてみると、Li2CO3という組成式になります。
ここまでで組成式や分子式の概要が分かってきたかと思います。
次は例題を通して理解をさらに深めましょう。
組成式の書き方の例題:炭酸ナトリウム
組成式の作り方の問題でよく出題される炭酸ナトリウムを求めてみましょう。
炭酸ナトリウムは、ナトリウムイオンと炭酸イオンから構成されていて、それぞれのイオン式はNa+、CO32-です。
ナトリウムイオンは+1の電荷を持ち、炭酸イオンは-2の電荷を持っています。
ナトリウムイオンと炭酸イオンを、2:1の比率で組み合わせることにより電荷を中和できるため、Na2CO3という組成式が導き出せます。
化学式を与えられていない場合には、イオン式を覚えていないと、陽イオンと陰イオンをどのような比率で組み合わせたらよいかがわかりません。基本的なイオン式は覚えておくようにしましょう。
3.組成式と分子式の違いとは?
組成式のほかにも、化学式について話題にするとき、よく登場する式が分子式です。
分子式は、組成式とは異なります。
分子式は、その名の通り、分子の化学式のことです。
分子とは、原子が結合してできた物質の最小単位を示しています。
例えば、空気を構成している主成分である窒素は、窒素原子が二つ結合することによりN2という窒素分子を形成しています。
酸素についても同様に、酸素原子が二つ結合してO2という酸素分子となっています。
このN2やO2は、それぞれ窒素分子、酸素分子の分子式です。
これに対して、例えば鉄の場合には、原子が構成単位となっていて化学式はFeになり、分子ではないので分子式はありません。
このような単一の元素で構成されている物質について、組成式を問われることはあまりありません。
ただし、厳密に表現するなら、窒素分子はN、酸素分子はO、鉄はFeになります。
また、陽イオンと陰イオンの組み合わせで作られている金属塩についても同様です。
例えば、塩化カリウムはKClが化学式ですが、分子式はなく、組成式は化学式と同じKClになります。
酢酸と水の場合の分子式・組成式
組成式や分子式の概要が分かったので、次は例題を通して理解をさらに深めましょう。
酢酸と水は、組成式に関わるテーマでよく出題されます。
酢酸の化学式はC2H4O2、水の化学式はH2Oですが、それぞれの分子式と組成式を求めてみましょう。
酢酸は分子なので分子式があり、化学式と同じC2H4O2になります。
より構造がわかりやすいようにCH3COOHという書き方をする場合もありますが、特に問題文中に指示がない場合には、どちらを答えても大丈夫です。
一方、組成式は、C2H4O2ではありません。
炭素、水素、酸素の数を見てみると、2:4:2です。
公約数の2で割れるとわかるでしょう。
ここで、炭素と水素と酸素の比が1:2:1だとわかります。
もうこれよりも小さな数で比にすることはできないので、酢酸の組成式はCH2Oです。
次に、水についてです。
水も分子なので分子式があり、化学式と同じでH2Oです。
組成式は、水素と酸素の比が2:1で、化学式にあるそれぞれの元素の数に一致するため、H2Oになります。
このように、分子式と組成式が一致することも多くあるので、混乱しないようにしましょう。
塩化ナトリウムの場合の分子式・組成式
組成式に関する問題では、塩化ナトリウムの問題もよく出題されます。
塩化ナトリウムの化学式はNaClですが、その分子式と組成式を求めてみましょう。
塩化ナトリウムは、陽イオンと陰イオンの組み合わせによって作られている塩です。
陽イオンはナトリウムイオンで、Na+と表記します。
陰イオンは塩化物イオンで、Cl–と書きます。
イオンによって構成されている塩化ナトリウムは、分子ではないので、分子式はありません。
組成式は、ナトリウムイオンと塩化物イオンの比を考えれば大丈夫です。
この例では、化学式と同じでNaClになります。
基本的に、陽イオンと陰イオンの組み合わせで作られている物質は、そのイオンが無数に規則正しく連なってできているのが特徴です。
その最小単位を化学式として定めているので、組成式は化学式に一致すると覚えておくと良いでしょう。
4.覚えておきたい組成式の一覧表
陽イオン、陰イオンを組み合わせることでさまざまな組成式が作れるようになりました。
以下の表は実際に陽イオンと陰イオンを組み合わせた組成式とその名称です。覚えておきたい組成式をピックアップしたので確認していきましょう。
まとめ:組成式の意味がわかれば求めるのは簡単
物質の組成式を求める問題は、高校化学でよく出題されます。
陽イオンと陰イオンを覚え、比例計算をして組み合わせれば、組成式を出すことは簡単です。
また、分子の場合には、分子式の各元素の数を見て約分すれば組成式になります。
このような求め方をマスターして、さまざまな物質を構成しているイオンの種類や化学式、分子式から、組成式を求められるようになりましょう。