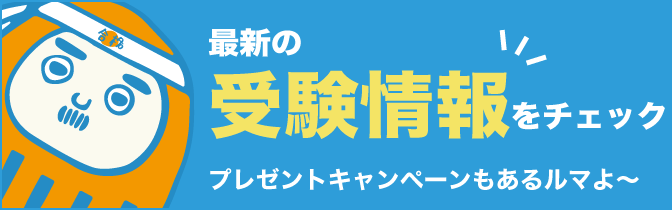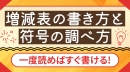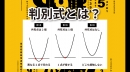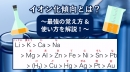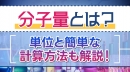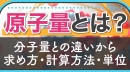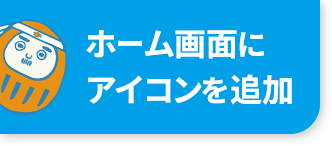金属のイオン化傾向の覚え方は?語呂合わせや金属の反応性について解説!

「イオン化傾向の順番が覚えづらい」「覚えても使い方が分からない」などのように、語呂合わせでの覚え方や活用方法がややこしく、分からなくなってしまっている方も多いのではないでしょうか。
イオン化傾向とは、溶液中において金属元素の陽イオンになりやすさを示したものです。金属を酸などの溶液に入れると、原子が電子を奪われ、陽イオンになって溶け出しますが、元素の種類によってイオン化のしやすさ(傾向)は全く異なっています。
練習問題を基に、イオン化傾向の活用方法を解説していくので、この機会に苦手意識を克服しましょう。また、イオン化は化学分野の基礎となってくる単元です。この記事を最後まで読んで点数アップに役立ててください。
・イオン化傾向の語呂合わせでの覚え方
・イオン化傾向の性質と反応の挙動
・イオン化傾向とイオン化エネルギーの違い
【PR】勉強を効率的に継続して、志望校に合格したい方必見!

↓無料ダウンロードはこちら↓
▶イオン化エネルギーとは?電子親和力との違いや求め方と覚え方を図説します!
▶イオン化とは?イオン化傾向についても解説!
▶ボルタ電池とは?イオン化傾向も含めて解説!
1.イオン化傾向の覚え方は「りっちにかそうかな」
2.イオン化傾向とは金属が陽イオンに変化する性質
2-1.常温の水との反応
2-2.熱水や高温水蒸気との反応
2-3.酸との反応
2-4.酸化力の強い酸との反応
3.イオン化傾向と電池のセンター試験問題を解いてみよう!
4.イオン化傾向とイオン化エネルギーは別物
5.まとめ
イオン化傾向の覚え方は「りっちにかそうかな」
イオン化列の語呂合わせは、「リッチに貸そうかな まああてにすんな ひどすぎる借金」です。
このようにイオン化傾向の大きい金属から順に並べたものを、金属のイオン化列といいます。
語呂合わせの中の「貸そう か」で K→Ca の順になることや、「(ま)あ あ(てに~)」で Al→Zn の順になるところは少し混同しやすいので、注意して覚えるようにしてみてください。
イオン化傾向とは金属が陽イオンに変化する性質
イオン化傾向とは、溶液中における金属元素の原子の陽イオンになりやすさを示したものです。
ここで、勘がいい方なら「イオン化傾向とイオン化エネルギーって同じじゃないの?」と思うのではないでしょうか。確かに、原子から電子が抜き取られて陽イオンになるという点は共通しているのですが、実は定義からして違います。
イオン化傾向とイオン化エネルギーの違いについては、あとの章で詳しく解説します。では、イオン化傾向が違ってくると各元素がどんな物質と反応するようになるのでしょうか。
常温の水との反応
Naよりイオン化傾向が大きい金属は、常温の水と反応し、水素を発生して水酸化物を生成します。
例えば、Kと水との反応式は以下のようになります。
2K + 2H2O → 2KOH + H2
NaとKは水と激しく反応し、Liは水と穏やかに反応します。
熱水や高温水蒸気との反応
Mgは熱水(沸騰水)と反応して、水素を発生して水酸化物を生成します。反応式は以下のようになります。
Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2
また、Mgよりイオン化傾向が小さい、Al、Zn、Feは高温の水蒸気と反応して、水素を発生して水酸化物を生成します。
例えば、Alと高温の水蒸気との反応式は以下のようになります。
2Al + 3H2O → Al2O3 + 3H2
酸との反応
水素よりイオン化傾向が大きいLi~Pbまでの金属は、水素より強い還元力があるので、H+をH2に還元することができます。
そのため、希塩酸などの薄い酸と反応し、水素を発生しながら溶け、塩化物や硫化物を生成します。
例えば、Naと希塩酸との反応式は以下のようになります。
2Na + 2HCl → 2NaCl + H2
一方、水素よりイオン化傾向が小さいCu~Auまでの金属は、希塩酸などの薄い酸に溶けません。
酸化力の強い酸との反応
水素よりイオン化傾向の小さいCu~Auまでの金属の中で、Cu、Hg、Agは、熱濃硫酸や濃硝酸、希硝酸などの酸化力の強い酸と反応します。
以下に、Cuと熱濃硫酸、濃硝酸、希硝酸との反応を示します。
① Cuと濃硫酸の反応
Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + 2H2O + SO2
② Cuと濃硝酸の反応
Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2
③ Cuと希硝酸の反応
3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO
また、Pt、Auは、王水(濃硝酸と濃塩酸の体積比1:3の混合物)には溶けます。さらに、Al、Fe、Niは、希硝酸とは反応しますが、濃硝酸には溶けません。
これは、金属の表面に安定で緻密な酸化被膜が生じ、内部を保護するためです。この状態を不動態といいます。
以上のことをまとめると、表のようになります。
金属元素の反応を理解する上で重要になるものなので、しっかりと覚えておきましょう!
イオン化傾向と電池のセンター試験問題を解いてみよう!
ここではイオン化傾向にまつわる問題を紹介します!
例えば、銅(Cu)とマグネシウム(Mg)に関して二つの反応式があります。
①Mg + Cu²⁺ → Mg²⁺ + Cu
②Mg²⁺ + Cu → Mg + Cu²⁺
化学反応式としてはどちらも成立しますが、実際に反応が進むのはどちらでしょう?
正解は①。理由は、銅よりマグネシウムの方が、イオン化傾向が大きいからです(不安な人は先ほどの語呂合わせをもう一度確認してみてくださいね!)。
②の式では、既にマグネシウムが陽イオンの状態で存在しているため、よりイオン化傾向の小さい銅がイオン化することはない、というわけです。
異なる二種類の金属元素が存在しているとき、イオン化傾向が大きい金属のほうが優先して陽イオンになる、という原則さえ覚えておけば、こういった問題で悩まされることもなくなりますよ!
そして、イオン化傾向を利用した例としてよく出てくるのが電池です。二種類の金属を電解質の水溶液に浸し、それらを導線でつなぐと、電子の流れが生じて電気を取り出すことができます。これが電池の仕組みです。
二種類の金属のうち、イオン化傾向が大きいほう(図中のZn)で電子を放出する酸化反応が起こり、陽イオンが水溶液中に溶け出します。その後、元素が持っていた電子が導線を通ってもう片方の金属(Cu)へと流れ、水溶液中の陽イオンが電子を受け取る還元反応が起こります。このサイクルによって電流が生じているのです。
イオン化傾向が大きい金属から小さい金属へと電子が流れているということは、イオン化傾向の大きい金属が電池の負極になるということです。ここはかなり問われやすいところなので、間違えないように気を付けましょう!
センター試験でもイオン化傾向・電池を扱った問題は頻出です。代表的な問題を見ていきましょう。まずは、H29年度の大学入試センター試験(追試験)「化学基礎」で出題されたものです。
見ての通り、この問題は2-4の表を覚えておけばすぐに解けますね!裏を返せば、しっかり覚えていないとこのような問題には手がつけられないので、確実に覚えるようにしましょう。(ちなみに正解は⑧です)
次に、2020年度の大学入試センター試験(本試験)の「化学基礎」では、電池の基礎知識に関する以下のような問題が出題されました。
問5 化学電池(電池)に関する記述として誤りを含むものを、次の①〜④のうちから一つ選べ
①電池の放電では、化学エネルギーが電気エネルギーに変換される。
②電池の放電時には、負極では還元反応が起こり、正極では酸化反応が起こる。
③電池の正極と負極との間に生じる電位差を、電池の起電力という。
④水素を燃料として用いる燃料電池では、発電時(放電時)に水が生成する。
それぞれの選択肢を見ていくと、
① 「電池の放電では、化学エネルギーが電気エネルギーに変換される」ので正しい。
② 放電時は、負極で電子を放出する酸化反応、正極で電子を吸収する還元反応が起こっているので、選択肢の文章は逆。よって、間違い。
③ 起電力とは、電池の正極と負極との間に生じる電位差のことなので、正しい。
④ 水素を燃料として用いた燃料電池では、水素の燃焼熱を電気エネルギーに変換します。そのため、発電時には水が生成するので、正しい。
以上より、答えは①となります。
また同年の大問2の問6でも、以下のようなイオン化傾向に関する問題が出題されています。
問6 金属の溶解を伴う反応に関する記述として正しいものを、次の①〜④のうちから一つ選べ。
①硝酸銀水溶液に鉄くぎを入れると、鉄が溶け、銀が析出する。
②硫酸銅(Ⅱ)水溶液に亜鉛板を入れると、亜鉛が溶け、水素が発生する。
③希硝酸に銅板を入れると、銅が溶け、水素が発生する。
④濃硝酸にアルミニウム板を入れると、アルミニウム板が溶け続ける。
ここで出てくる、銀(Ag)、鉄(Fe)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、水素(H)、アルミニウム(Al)のイオン化傾向は、先ほどの順番から
Al > Zn > Fe > H > Cu > Ag
なので、それぞれの選択肢を見ていくと、
① Fe > Agなので、「鉄が溶け、銀が析出する」は
正しい。
② Zn > Cuなので、「亜鉛が溶け、水素が発生する」は
間違い。実際は、亜鉛版に銅が析出して、赤褐色になります。
③ H > Cuなので、「銅が溶け、水素が発生する」は
間違い。実際は以下のような反応をして、一酸化窒素を生成します。
3Cu + 8HNO3 → 2NO + 4H2O + 3Cu(NO3)2
④ Al > Hなので、濃硝酸にアルミニウム板を入れると溶けるのでは?と思いますが、実は溶けません。これは、濃硝酸にアルミニウム板を入れると、すぐに表面に緻密な酸化被膜(酸化アルミニウム)が形成されて、不動態となっているからです。したがって
間違いとなります。
よって、問題の答えは①です。
以上のように、イオン化傾向や電池の問題はセンター試験では頻出の単元ですので、きちんと覚えておくようにしましょう。
イオン化傾向とイオン化エネルギーは別物
イオン化傾向は、金属の「単体」が「水和」イオンになるのに必要なエネルギーであり、イオン化エネルギーは、「気体」状態の金属原子から電子をとり去るのに必要なエネルギーのことを言います。
ちなみに、単体の金属が水和イオンになるためには、次の3つの過程を経ることになります。
① 金属単体(固体)中の結合をすべて切り、バラバラの金属原子(気体)にする。
② 金属原子から電子をとり去って金属イオンにする。
③ 金属イオンを水中に導いて水和イオンにする。
各段階において、①昇華熱、②イオン化エネルギー、③水和熱が必要になるので、イオン化傾向は、これらのエネルギーの総和となります。
一般的に、イオン化エネルギーが小さい金属ほどイオン化傾向が大きくなりますが、食い違う部分も見られます。したがって、イオン化傾向とイオン化エネルギーは異なるものであるということです。
少し難しいなと思う人は、最低限「イオン化傾向とイオン化エネルギーは似ているけど、同じものではない」ととらえておいてください。
もしイオン化エネルギーについて、まだしっかり理解できていないという方がいたら、イオン化エネルギーとは?電子親和力との違いや求め方と覚え方を図説します!の記事を読んでくださいね!
まとめ
このように、電池をはじめとした金属の反応に関する範囲では、イオン化傾向の大小を知っていないと解けない問題がたくさん出てきます。センター試験や二次試験でも頻出の範囲ですので、まずはイオン化列を覚えることからはじめて、どんな問題でもしっかり対応できるよう勉強していきましょう!
しっかり覚えて問題演習を重ねる、それだけで化学はかなりの問題に対応できるようになりますよ!みなさんの頑張りを応援しています。