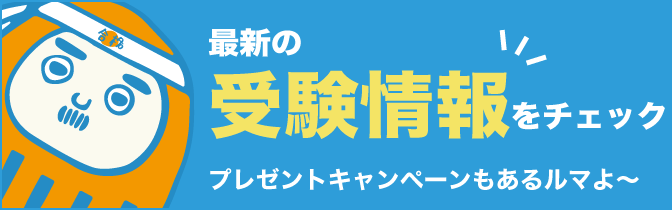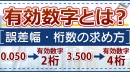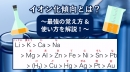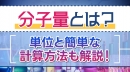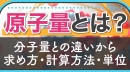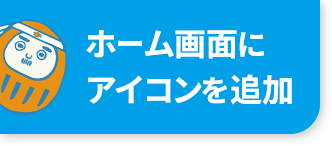アンモニアの性質を知ろう!気体を集める方法や有名な実験も紹介

アンモニアは工業的にも重要な物質であり、実際に多くの工業的な手法の材料にも使用されています。
そんなアンモニアには、他の気体にはない、独自の性質や特徴があります。今回はアンモニアの性質や特徴を、出題での要点になる実験系を用いてわかりやすく解説いたします。
【PR】勉強を効率的に継続して、志望校に合格したい方必見!

↓無料ダウンロードはこちら↓
【 目次 】
2. アンモニアを集める方法
2-1. 水上置換法
2-2. 漸化式と極限
2-3. 上方置換法
3. アンモニアの性質を利用した有名な実験
3-1. アンモニアの噴水実験
3-2. アンモニアの作り方
3-3. アンモニアを工業的に集める方法
1. アンモニアの性質
アンモニアは以下の4つの性質を持つ気体です。
1. 無色、透明の気体、卵を腐らせたような刺激臭(腐卵臭)
2. 空気よりも軽い
3. 水に非常に溶けやすい
4. 塩基性の性質を持つ
アンモニアは無色透明な気体です。しかし、強烈な刺激臭があり、非常に強い毒性があります。そのため、直接臭いを嗅ぐことは大変危険です。卵や生ゴミが腐ったときの腐卵臭に近い臭いがすることで知られています。
空気よりも軽い理由はずばり、アンモニアと空気を分子の原子数で表すとわかりやすくなります。
アンモニアはNH3という分子式で表すことができます。窒素原子は1原子数7、水素は原子数1であり、合計の質量は10です。空気に主に存在している、酸素分子の質量数は16、窒素原子は14です。そのため、アンモニア分子は、大気中よりも軽いため、空気よりも軽い気体になります。
アンモニアは窒素原子に水素原子と共有結合で結合しています。しかし、水分子が存在すると水分子の一つの水素原子と結合し、アンモニウムイオンと水酸化物イオンになります。
NH3+H2O→NH4++OH−
このため、アンモニアは水に非常に溶けやすく、溶けたときに水酸化物イオンが反応でできます。そのため、強い塩基性の性質を持つのです。
水と反応することで塩基性になるため、あらためて、直接嗅ぐことは大変危険です。人間の鼻粘膜には水蒸気が存在しているので、鼻の中の空気中の水蒸気と反応して、皮膚に炎症が起こるからです。
2. アンモニアを集める方法
実験でアンモニアの気体を集める方法には、水上置換法、下方置換法、上方置換法の3種類があります。
2-1. 水上置換法
水上置換法とは、気体を集める容器に経路を水で満たし、気体が発生した地点からの管から発生する気体を集める方法です。
水上置換法のメリットは、水に満たした経路を通ることで、集めたい気体のみを回収できることです。他の分子の混じりをなくした状態で集めることができます。水上置換で集めるときは反応直後の空気を回収するのではなく、管に残っている空気を水中に出してから、回収を始めることで、不純物が限りなく少ない気体を得ることが可能です。主に、酸素や窒素、水素、水に溶けない気体に向いている方法です。
2-2. 下方置換法
下方置換法とは、気体を集める地点を気体を発生する地点よりも低くし、管から発生する気体を容器に集める方法です。
酸素や窒素に比べて、分子量が重い分子を集める場合に使用され、集める容器と管の口は下に向けて集めます。水に溶けてしまう空気よりも重い気体二酸化炭素などに向いています。
2-3. 上方置換法
上方置換法は発生源から、気体を集める容器の口や容器を上向きに固定して、気体を集める方法です。
酸素や窒素よりも軽く水に溶けてしまう分子に使用される置換方法です。アンモニアのような気体に使用されます。
3. アンモニアの性質を利用した有名な実験
3-1. アンモニアの噴水実験
アンモニアの噴水実験で使用するもの
- フェノールフタレインを入れた水
- アンモニア
容器にアンモニアを溜め、アンモニアと水を反応させます。この時2つの変化が同時に起こります。
- アンモニアが入っていた容器が真空になります。
- アンモニアが溶けたことによって水酸化物イオンが産生します。
1に関しては、アンモニアが容器内に充満していた状態が気体から液体として溶解します。同じ分子数を集めて、気体と液体の体積を比較した場合、液体の体積が小さくなります。その結果、アンモニアの気体が液体の水に溶けると、アンモニアが入っている容器のアンモニアの体積が小さくなります。ですが、フラスコの形が変化しないのは「ボイル・シャルルの法則」により、減った分だけの体積を圧力で補うため、見た目上の体積には変化が起きないからです。実際に起こっている現象は、アンモニアが含まれている容器の気圧が溶解によって低くなり、真空に近づくということです。真空になると、もう一方の口から圧力を均一にするために、水の容器から水を吸い上げます。
アンモニアが溶けることで、容器に入った側の液体で化学反応し、水酸化物イオンができます。この結果、塩基性になります。フェノールフタレインは、塩基性になると赤く変色する性質があるため、変化するのです。
そのため、アンモニアが水と反応することで、水を吸い上げ、吸い上げた水が赤い色に変色する現象が発生します。
3-2. アンモニアの作り方
アンモニアを実験で作る場合の代表的な反応は、以下の化学式になります。
Ca(OH)2+2NH4Cl→CaCl2+2NH3+2H2O
水酸化カルシウムと塩化アンモニウムを加熱することで、塩化カルシウムとアンモニアと水を得ることができます。
ここで注意点があります。
まずは、試験管の口を下げることと、上方置換法で集めるようにすることです。これは、反応する場所に比べて口を下げることで、空気より軽いアンモニアの気体を集めやすくなるからです。そして、アンモニアは水に溶けやすいため、上方置換法で集めることになります。
反応式に水が発生するため、ソーダ石灰など吸湿剤を反応の途中で通すことも大切なポイントです。
①空気が軽い気体であること ②反応中に水が発生するので、水分をしっかり取り除く反応系にすること。これが大きなポイントです。
3-3. アンモニアを工業的に集める方法
先程の実験で発生させる方法は、少量の収集に向いています、工業的には、安価な材料で多量のアンモニアを作成するため、「ハーバーボッシュ法」が用いられます。
窒素と水素の混合気体から四酸化三鉄を触媒にして反応させて産生させます。
ハーバーボッシュ法について詳しく知りたい方は、「炭酸ナトリウムを造る!!アンモニアソーダ法の化学反応と反応順のポイント」の記事をご覧ください。
ハーバーボッシュ法は反応途中で、塩化水素との反応があり、塩化アンモニウムが発生します。塩化アンモニウムは白煙のため、アンモニアが作成されているかどうかの検出方法として頻出なので、しっかり覚えておきましょう!
4. まとめ
アンモニアは空気よりも軽く、水に溶けやすく、塩基性の液体となります。空気は無色透明であるものの、強烈な刺激臭を放ちます。
性質上、上方置換法で集める必要があり、フェノールフタレイン液と反応をすると赤色になります。
水との強い反応を持つため、アンモニアの噴水実験が問題として頻出ポイントです。アンモニアが水と溶けることで、気圧が減少し、水を吸い上げる反応と塩基性に水が変化する反応が同時に発生します。
実験室でアンモニアを生成する場合、水酸化カルシウムと塩化アンモニウムとの加熱反応が用いられますが、工業的に大量生成する場合は、窒素と水素の安価な材料でアンモニアを作るハーバーボッシュ法が用いられます。
アンモニアの性質を理解し、実験やテストに備えておきましょう。