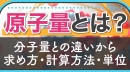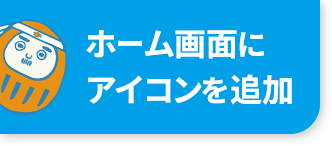電気分解とは?電気分解を理解して定期テスト10点アップ

「水を電気分解すると酸素と水素が発生する」という問題は、中学理科でも出てくる有名な話ですね。
高校化学で「電気分解」という項目を習うと、今度は反応式についても理解しなければなりません。
今回は、電気分解の実験で代表的な水の電気分解と、工業利用されている銅の電気分解を例に挙げながら説明していきたいと思います。
【PR】勉強を効率的に継続して、志望校に合格したい方必見!

↓無料ダウンロードはこちら↓
1.基本的な電気分解の仕組み
電気分解とは、電解質の溶液に電極を差し込み電流を流すと、電極と溶液の間で酸化還元反応が起きて、電解質が分解されるという現象です。
この反応は、電池で起こる酸化還元反応と似ていますが、決定的に違う点が1つあります。それは、不可逆反応であるということです。
電気分解では、水分子のように、酸素と水素がそれぞれ安定な状態でいるような物質に強制的にエネルギーを与え、化合物を分解します。
一方の電池の場合は、酸化還元反応という自然界でも一般的な反応を起こさせて、電気を取り出しています。
電気分解や電池では、2つの電極のうち、電源のプラス極に接続された方を陽極といい、マイナスに接続された方を陰極と言います。
電流がプラスからマイナスに流れると、電子は反対のマイナスからプラスに移動します。
したがって、陰極では電子を受け取り、還元反応が起きます。
反対に陽極では、電子を放出しているので酸化反応が起きます。
電気分解の優れた利点は、与えるエネルギー量によって、分解する化合物の種類を選択することができるということです。
そのため、電気分解では、得られる単体物質の純度が比較的高いといえます。
この特徴を利用して、様々な金属塩が溶けた液体から特定の金属成分のみを陰極に析出させ、金属精錬を行ったり、NaCl水溶液を電気分解して塩素を陽極から取り出したりすることができます。
ただし、電気分解で溶かす金属塩や電極は、なんでもいい訳ではありません。
電気分解が行われる金属塩の溶液のことを電解液と呼びますが、電解液には水溶液中で電離する物質が使用されます。
例えば、NaCl や NaOH、硫酸塩などです。
また、電気分解に用いる電極も、その材質に注意しなければなりません。
その説明をするために、まずは、イオン化傾向について覚えておきましょう。
イオン化傾向とは、金属が他の金属(&水素)と比較して酸化しやすいのか還元しやすいのかを表す性質です。
覚え方はいろいろありますが、筆者は下記のゴロ合わせで暗記しました。
ネットで調べてみると、他にも覚え方があるようなので、ご自分の覚えやすいもので暗記してください。
かそう(カリウム,K) か(カルシウム,Ca) な(ナトリウム,Na)
ま(マグネシウム,Mg) ぁ(アルミニウム,Al)
あ(亜鉛,Zn) て(鉄,Fe) に(ニッケル,Ni) する(すず,Sn) な(なまり,Pb)
ひ(水素,H) ど(銅,Cu) す(水銀,Hg) ぎる(銀,Ag) 借(白金,Pt) 金(金,Au)
「貸そうかな、まあ当てにするな。ひどすぎる借金」
それでは、イオン化傾向を覚えたところで、本題に戻ります。
電気分解は、陰極と陽極それぞれに焦点を当てて考える必要があります。
陰極
陰極は、電極を考える必要はなく、どの水溶液が使われているかが重要になります。
上記でも述べたように、陰極は電子を受け取ります。
水溶液にCu2+やAg+など、H+よりもイオン化傾向が小さいイオンが含まれていた場合、そのイオンが反応して還元され、金属として析出されます。イオン化傾向の名前の通り、イオン化傾向が大きい方がイオンのままでいようとする力が大きいからです。
もし水溶液にH+よりもイオン化傾向が小さいイオンが含まれていなかった場合、水が反応します。
その時の反応式は以下の通りです。
- 水溶液が酸性の場合 → 2H++2e–→H2
- 水溶液が中性や塩基性の場合 → 2H2O+2e–→H2+2OH–
酸性の水溶液ということはH+が多いということですが、水溶液が中性や塩基性だった場合H+はほとんど存在していないので水が反応する反応式となります。
陽極
陽極の場合は電極をまず最初に考えます。
主にPtやAu、Cなどが電極の場合と、それ以外(CuやAgなど)が電極の場合の2パターンです。
- CuやAgなどが電極の場合
CuやAgは金属です。
金属は本来陽イオンになりやすいので、電極自身が反応します。
(ex) Cu → CU2++2e- , Ag → Ag+ + e–
- PtやAu、Cなどが電極の場合
PtやAuなどはイオン化傾向がとても小さいです。そして、Cは炭素であるため金属ではありません。
そのため、電極がイオンになって反応することはありません。
この時は溶液中のイオンが酸化されます。
- 水溶液中にCl-などハロゲン化物イオンが含まれている時
Cl–はハロゲン化物イオンです。ハロゲン化物イオンはとても酸化されやすいので、Cl–が水溶液中に含まれている場合は酸化されて塩素が発生します。この時の反応式は以下の通りです。
2Cl–→Cl2+2e–
- それ以外のとき
ハロゲン化物イオンが含まれていない場合、水が分解されます。
しかし、水溶液が中性や酸性の場合、OH–はほとんど存在していないので、塩基性の場合と中性・酸性の場合の2パターンにわけて考えなくてはいけません。
・水溶液が塩基性の場合
4OH–→O2+2H2O+4e–
・水溶液が中性・酸性の場合
2H2O→02+4e–+4H+
どちらの場合も酸素が発生していることがわかります。
2.電気分解の実験の例
ここでは説明のために、水の電気分解と、銅板を極とした電気分解について説明します。
2−1. 水の電気分解
水の電気分解では、純粋な水は電気を通さないため、NaOHを加えて電気を通す状態にしておきます。
H2O → H++ OH–
電解質を加えた水に電流を流して電気分解すると、水は酸素と水素に分解されます。
ここからは、電気分解の反応式の作り方を順を追って説明します。
まず、水は液体中では電離して水素イオンと水酸化物イオンに電離しています。
H2O → H++ OH–
陰極(-)では、電子が供給されるため水溶液中の陽イオンが集まり、電子を受け取ってより安定な状態に化学変化します。
これを、還元反応と言います。
水の場合、水素イオンが還元されてより安定は水素分子になります。
2H++ 2e– → H2
一方、陽極では、陰イオンが集まり、陰イオンが電子を放出してより安定な状態に化学変化します。
これを酸化反応と言います。
片割れの水酸化物イオンが電子を放出し、酸素分子になります。
2OH– → O2 + 2H++ 4e–
このままでは水素イオンが残るので、陽極の周りに水酸化物イオンが豊富にあると仮定すると、反応式は最終的に下記になります。
4OH– →O2 + 2H++ 2OH–+4e–
4OH–→ O2 + 2H2O + 4e–
そして、陰極と陽極で進行するそれぞれの化学反応を合わせると、電子を相殺するように係数を調整して、下記のようになります。
4H+ + 4e–+ 4OH– → 2H2 + O2+ 2H2O + 4e–
4H2O → 2H2 + O2 + 2H2O
2H2O → 2H2 + O2
この式から分かる通り、水を電気分解すると水素と酸素が発生し、水 2molに対して水素が2モル、酸素が1モル生成されます。
気体の体積比も同じ比になるので、水素:酸素=2:1で体積が変化します。
2−2. 銅の電気分解(粗銅と純銅の電解精錬)
冒頭でも述べたように、電気分解という手法は、簡単に大量の単一成分を溶液中から固体として析出させる技術です。
次に、有名な銅の電気分解(電解精錬)について説明します。
極板には銅板を用いますが、陰極側は純銅という、銅の純度が比較的高い銅板を用います。
一方、陽極には粗銅と言ってFe、Al、Znなどの不純物を含むような銅板を用います。
電解液には、一般的には硫酸銅が用いられる場合が多いです。
この状態で回路をつないで電気を流すと、陰極では還元反応が進行し、陽極では酸化反応が進行します。
陰極(還元反応) Cu2+ +2e– →Cu
陽極(酸化反応)Cu → Cu2+ +2e–
陰極では、電解液中の銅イオンのみが析出するため、純度が高い銅が得られます。
この銅は目的に応じてさらに純度を高められます。
陽極では、銅が析出して電解液中に溶出します。
このとき、粗銅板の表面に付着していた雑多な金属物質が剥がれ落ち、陽極板の下には泥塊(でいかい)ができます。
この泥塊を、陽極泥といいます。
陽極泥中には、極々微量ですが貴金属(金、銀、その他プラチナグループと呼ばれるレアメタル等)が含まれており、この泥塊を回収して分離精製し、副産物を得る工場もあります。
このようにして、銅は電気分解されます。
銅の電気分解のポイントは、粗銅と純銅という2種類の銅の極板を使って電気分解を行うという点です。
紛らわしい点もいくつかありますが、整理して覚えましょう。
3.電気分解とファラデーの法則
さて、これまでの説明から、電解質に電気を流すと、電解質が分解されて化学反応が起きることがわかりました。
次に、この電気分解によって目的の物質を得るためには、どれくらいの電気を流したらよいのか?ということを考えていきたいと思います。
ここで、ファラデーの法則を紹介します。
ファラデーの法則とは、ざっくり言うと、1molの電子を動かすのに96500 C(クーロン)という電気量を流す必要がありますよ、という法則です。
この法則はこれだけで、あとは自分で使いこなす必要があります。
注意してほしいのが、電流は基本的には単位はアンペアですが、クーロンは電気の量なので同じではありません。
アンペアとクーロンの関係は次のようになります。
1[A]=1[C⁄s]
1秒あたり電気を1Cだけ流した時の電流の大きさが、1Aなのです。
このことを踏まえて、以下の例題にチャレンジしてみましょう。
練習問題
硝酸銀の半反応式は以下のようになる。
Ag=108 g/mol、ファラデー定数, F=9.65×104 C/molとする。
Ag+ +e– →Ag
(1)10Aの電流をある時間だけ通電させて電気分解を行った結果、負極版の重さが3.6g増加した。何秒間通電したか?
(2)通電時間を1.9×103sとしたとき、析出量は7.2gであった。通電した電流は何Aか?
解答と解説
(1)電子1モルで、銀1モルが析出する。
析出した銀の物質量と、電気量が等しいので、
∴ t = 3.2 × 102 s
(2)同様に考えると、
∴ I = 3.4 A
電気分解のまとめ
電気分解は、中学理科で簡単な水の電気分解を習い、高校では銀、銅、ハロゲン化物を含む電解質の電気分解を習います。
本質はイオン化傾向に基づいて酸化還元反応が起きるということなので、この大原則を忘れずに、練習問題をたくさん解いて力をつけましょう。