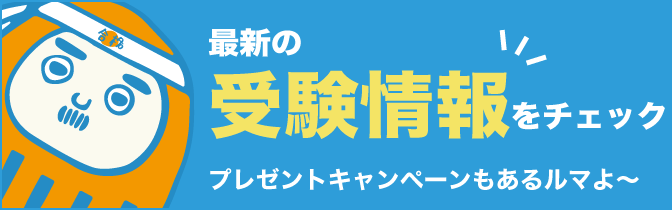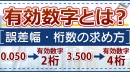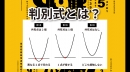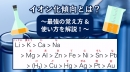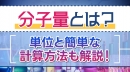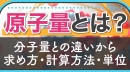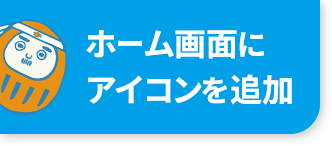イオン結晶とは?イオン結晶のポイントを分かりやすく解説

高校化学の試験では化合物の結晶に関する問題が出題されることがあります。
ここでは結晶の種類のひとつであるイオンの結晶について説明をしていきます。
結晶は単純な構造の繰り返しですので、基本の考え方が一度分かればそれほど苦労せず問題が解けるようになるでしょう。
【PR】勉強を効率的に継続して、志望校に合格したい方必見!

↓無料ダウンロードはこちら↓
1.そもそもイオン結合とはなにか?
まずは、結晶を説明する前に、化合物の結晶を形成するイオン結合とは何かについて解説していきます。
イオン結合は、陽イオンと陰イオンが静電気的な引力で引き合ってできている結合のことです。
それぞれ金属と非金属が結合していることが特徴で、静電気的な力のことをクーロン力とよんでいます。
代表的なイオン結合の物質の組成式は
NaCl、KI、CaCO3、NaCl 、Al2O3、NaNO3などがあります。
組成式についてはこちらで詳しく説明していますので、よければ参考にしてください。
2.イオン結晶とはなにか?
それではイオン結合を知った上で、イオンの結晶とはどのようなものなのかを解説します。
基礎的な部分から丁寧に考えていきましょう。
まず、物質は原子の結晶の集まりから構成されています。
次に、我々が用いている組成式は、その原子の集まりの最も小さい単位となります。
そして、結晶は、組成式1つの構造を表したものです。
今回説明するイオン結晶も同じ考え方で、陽イオンと陰イオンで構成された結晶のことをいいます。
それぞれの結晶には特徴がありますが、イオン結晶は、硬くてもろいのが特徴で、強い力を加えると、特定の面にそって割れやすい性質があります。これを「へき開」と呼びます。
また、沸点・融点が高い傾向もあります。
また、イオン結晶の構造は次のような3種類にわけられ、代表的な化合物の名前がつけられています。
- 塩化ナトリウム型構造(NaCl型構造)
- 塩化セシウム型構造(CsCl型構造)
- 硫化亜鉛型構造(ZnS型構造)
これから、この3種類のイオン結晶の構造について詳しく説明をしていきます。
3.イオン結晶でテストに出やすいポイントは?
各構造の説明に入る前に、イオン結晶について試験で出題される抑えるべきポイントを整理しておきましょう。
結晶に関する問題は、次のようなことを聞かれることがほとんどです。
- 単位格子あたりに含まれる陽イオン・陰イオンの数
一つの構造の中に、イオンが何個分含まれているか
- 配位数
対象のイオンと結合しているイオンの中で、最も近い距離にあるものの数
- 限界半径比
イオン同士がギリギリ接している時の、陽イオンのイオン半径と陰イオンの半径の比
考え方は各構造で使えますので、ひとつひとつ理解していけば、すべての回答できるようになるでしょう。
それでは、それぞれの構造や特徴を詳しくみていきます。
3-1.【イオン結晶】塩化ナトリウム型構造(NaCl型構造)
塩化ナトリウム型構造(NaCl型構造)は下の画像のように陽イオンと陰イオンが規則正しく並んだ形状をしています。
右図が実際のイオンの実寸方のままで表したもので、内部の構造がよくわからないので、構造をよくわかるようにするために隙間を開けて表したものが左図です。
黄色がNa+、青がCl–であるとします。
それでは抑えるべきポイントについて考えていきましょう。
- 単位格子あたりに含まれる陽イオン・陰イオンの数
まず、イオン結晶に含まれる陽イオンNa+と陰イオンCl–を数えます。
この数え方は簡単な数学と同じです。
塩化ナトリウム型構造(NaCl型構造)に含まれるNa+のうち、格子の各辺にあるものはNa+の1/4となっています。
これが各辺にあるので、正方形の辺の数は12であるから1/4×12=3
頂辺にあるNa+の数は合わせて3個です。
それに加えて、格子の中心にも1個ありますので、Na+の数は3+1=4個となります。
次に、Cl–の数について考えます。
各頂点にあるものはCl–の1/8となっているものです。
これが各頂点それぞれにあるので1/8×8=1個です。
また、面の中心にあるものはCl–の1/2となっています。
1/2したものが面の数の6個なので1/2×6=3個
以上より、Cl–の数は1+3=4個です。
- 配位数
配位数とは、1つの粒子に接している粒子の数のことです。塩化ナトリウム型構造(NaCl型構造)では、中心のNa+は周りの6個のCl–と接しており、Cl–も周りの6個のNa+と接しています。
そのため、各イオンの配位数は6となります。
- 限界半経比
イオン結晶の面をみると、イオン同士がギリギリ接している時のNa+・Cl–の関係を三平方の定理から求めることができます。
よって、限界半経比は0.414となります。
3-2.【イオン結晶】塩化セシウム型構造(CsCl型構造)
塩化セシウム型構造(CsCl型構造)は下の画像のように、陽イオンが中央に位置した構造となっています。
それではこちらも抑えるべきポイントについて考えていきましょう。
- 単位格子あたりに含まれる陽イオン・陰イオンの数
まず、イオン結晶に含まれる陽イオンCs+と陰イオンCl–を数えます。
塩化ナトリウム型構造(CsCl型構造)に含まれるCs+は、中央にある1個のみです。
次に、Cl–の数について考えます。
各頂点にあるものはCl–の1/8となっています。
1/8したものが各頂点にそれぞれあるので8×8=1個となります。
- 配位数
塩化セシウム型構造(CsCl型構造)では、中心のCs+は周りの8個のCl–と接しており、Cl–も周りの8個のCs+と接しています。
そのため、各イオンの配位数は8となります。
- 限界半径比
イオン結晶の対角面を使えば、イオン同士がギリギリで接しているときのCs+とCl–の関係を三平方の定理から求めることができます。

3-3.【イオン結晶】硫化亜鉛型構造(ZnS型構造)
硫化亜鉛型構造(ZnS型構造)は下の画像のように、陽イオンが格子内に配置されている結晶となっています。
黄色がZn2+で青がS2-です。
それでは抑えるべきポイントについて考えていきましょう。
- 単位格子あたりに含まれる陽イオン・陰イオンの数
まず、イオン結晶に含まれる陽イオンZn2+と陰イオンS2–を数えます。
Zn2+についてですが、単位格子内にZn2+が1個そのまま分割されず4個含まれているので、1×4=4個となっています。
次に、S2-の数について考えます。
S2-のうち、格子の頂点にあるものはS2-1/8となっており、各頂点それぞれにあるので1/8×8で1個です。さらにS2-のうち、面の中心にあるものは、S2-1/2となっており、各面にそれぞれあるので1/2×6で3個です。
よって、S2-の数は1+3で4個となります。
- 配位数
硫化亜鉛型構造(ZnS型構造)では、Zn2+は周りの4個のS2-と接しています。
同じくS2-も周りの4個のZn2+と接しています。
そのため、硫化亜鉛型構造(ZnS型構造)の各イオンの配位数は4となります。
- 限界半経比
イオン結晶の対角面を使えば、イオン同士がギリギリで接しているときのZn2+とS2–の関係を三平方の定理から求めることができます。
よって、限界半経比は0.225となります。
4.イオン結晶のまとめ
イオン結晶の特徴や抑えるべきポイントについて説明をしてきましたが、まとめると以下のようになります。
1.イオン結合は陽イオンと陰イオンがクーロン力と呼ばれる静電気的な引力で引き合ってつくる結合です。
2.イオン結晶とは、陽イオンと陰イオンで構成された結晶のことをいいます。
イオン結晶は次のような3種類の構造があります。
・塩化ナトリウム型構造(NaCl型構造)
・塩化セシウム型構造(CsCl型構造)
・硫化亜鉛型構造(ZnS型構造)
3. イオン結晶について試験で出題される抑えるべきポイントは、単位格子あたりに含まれる陽イオン・陰イオンの数、配位数、限界半径比です。
一見複雑に見えますが、結晶の考え方はすべて同じなため、一度覚えてしまえば簡単に問題を解けるようになると思います。
是非このページを復習に使って、得点源となる問題を1つ増やしてくださいね!