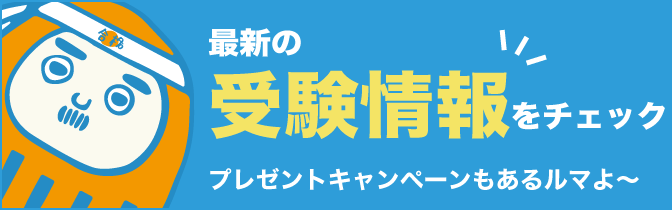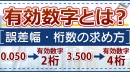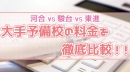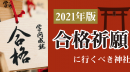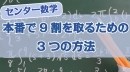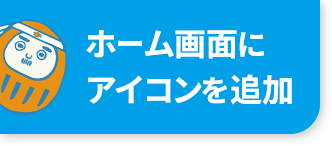夏祭りが試験にでるって知ってた?頻出の祭りの歴史から今年の日程まで紹介

みなさんは夏といえば何を思い浮かべますか?
海、花火大会、夏休み、そうめん、、、など色んな意見があると思いますが、筆者は夏祭りこそ夏の風物詩ではないかと思います!
実は祭りは、中学の地理の問題としても出題されるんです。
そこで今回は、2017年の全国の人気夏祭り日程一覧から、試験に頻出の祭りの歴史まで紹介したいと思います。
地理問題の対策だけでなく、今年の夏をより楽しむための夏祭り情報満載なので、ぜひ最後まで目を通してみてください!
1.2017年人気の夏祭り日程一覧
東北・関東・中部
| 青森ねぶた祭り | 青森県青森市 | 8/2~8/7 |
| 弘前ねぷた祭り | 青森県弘前市 | 8/1~8/7 |
| 秋田竿灯祭り | 秋田県秋田市 | 8/3~8/6 |
| 仙台七夕祭り | 宮城県仙台市 | 8/6~8/8 |
| 山形花笠まつり | 山形県山形市 | 8/5~8/7 |
| 深川八幡祭り | 東京都江東区 | 8/11~8/15 |
| 湘南ひらつか七夕祭り | 神奈川県平塚市 | 7/7~7/9 |
| 吉田の火祭り・すすき祭り | 山梨県富士吉田市 | 8/26・8/27 |
近畿・中国・四国・九州
| 祇園祭 | 京都市東山区 | 7/1~7/31 |
| 天神祭 | 大阪市北区 | 7/24・7/25 |
| 阿波踊り | 徳島県徳島市 | 8/12~8/15 |
| よさこい祭り | 高知県高知市 | 8/9~8/12 |
| 博多祇園山笠 | 福岡市博多区 | 7/1~7/15 |
2.試験頻出!東北三大祭りとは?
地理の試験には祭りに関する問題が出されることがあります。
そこで、試験によく出る東北三大祭りについて説明します。
東北三大祭りとは、①青森ねぶた祭②秋田竿灯祭り③仙台七夕まつりの3つを指します。
毎年大勢の観光客が訪れる日本を代表する有名な夏祭りです。
ちなみに、山形県の花笠まつりも含めて東北四大祭りと称されることもあるんだそうです。
では、それぞれの祭りについて詳しく紹介します!
3.青森ねぶた祭
ねぶた祭とは、毎年8/2~7に開催される青森県の名物祭りで、「ねぶた」と「ハネト」による伝統的なパフォーマンスを見に毎年たくさんの人が訪れます。
そもそも「ねぶた」とは、大きな張りぼて人形を乗せた山車のこと(上記写真のような)で、毎年約20台のねぶたが運行しています。
「ハネト」とは、「ラッセラー ラッセラー」という元気な掛け声とともにねぶたの周りを跳ね歩く踊り子のことです。
「ハネト」は一般の人でも自由に参加できるそうです。
ねぶた祭の歴史
享保年間(1716年~1735年)に、青森県油川町付近で弘前のねぷた祭りを真似て、人々が灯篭を持ち歩き踊ったのが始まりと言われています。
その頃のねぶたは京都の祇園祭の山車に似ていたそうです。
その後ねぶたは巨大化していき、明治時代には高さ十一間のものを100人で担いだと言われています。
しかし、明治新政府から任命された青森県令の菱田重喜によって明治6年に禁止令が出されたため、以降9年間ねぶたは姿を消しました。
復活したのは明治15年で、その後第一次世界大戦の影響で昭和20年にまた中止されましたが、翌21年には復活。
第二次大戦以降は観光化の影響もあってねぶたが更に巨大化し、現在のような姿になりました。
(青森ねぶた祭HP)
4.秋田竿灯祭り
竿灯祭りとは、竹を組んで沢山の提灯を吊るした竿灯を持って練り歩き、厄除けや五穀豊穣を願う祭りのことです。
竿灯は、最大高さ12メートル、46個の提灯を吊るし、幻想的な美しさを醸し出します。
それを職人が一人でバランスを取りながら支え、妙技を競い合うことも楽しみの一つです。
竿灯祭りの歴史
竿灯祭りの原型は、真夏の病魔や邪気を祓うためのねぶり流し行事であったそうです。
ねぶり流しとは、願い事を書いた短冊を竹に飾り、街を練り歩く行事でしたが、それが宝暦元年の蝋燭の普及やお盆の高灯篭と組み合わさって現在のような行事になったと言われています。
残っている最も古い文献には寛政元年頃の陰暦7月6日に行われたねぶり流しが紹介されています。
この時にはすでに秋田独自の風俗と伝えられており、今の竿灯祭りの原型が記されています。
(秋田竿灯祭りHP)
5.仙台七夕まつり
七夕は、一般的に7月7日の行事ですよね。
しかし、仙台の七夕まつりは8月に行われます。
その理由は、本来の七夕である旧暦の7月7日の季節感に合わせるために、新暦に一か月足した中歴を用いているためです。
仙台七夕まつりでは「笹飾り」と呼ばれる高さ10メートルほどの七夕飾りが美しく、豪華絢爛に祭りを彩ります。
仙台七夕まつりの歴史
七夕まつりは、仙台藩祖であった伊達正宗が婦女に対する文化向上の目的で七夕を推奨したため、行事としてさかんになったと言われていますが、詳細は不明です。
そんな七夕まつりは、維新や新暦採用、第一次大戦による不景気を経て、年々衰退する一方でした。
そこで、不景気を吹き飛ばそうと昭和2年、有志の仙台商人たちが七夕まつりを復活させました。
しかし、第二次大戦によって再び七夕まつりは姿を消してしまいました。
終戦後、焼け跡に竹飾りが立てられ、七夕祭りが復活。
その翌年の天皇の巡幸時には155本の竹飾りで天皇を迎えたことが話題となって、その後現在のような観光イベントへと発展しました。
いかがだったでしょうか?
中学生は地理の試験にも出題される可能性もあるので、画像とともによくチェックしておきましょう!
受験生も勉強の息抜きに、ぜひ夏祭りへ足を運んでみてくださいね!