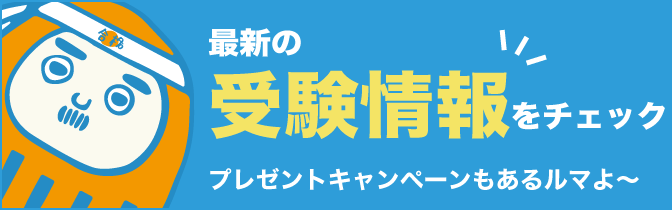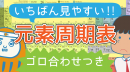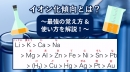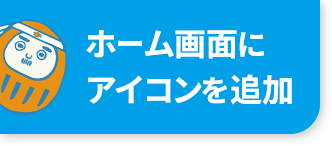返り点とは?白文の書き下し方を分かりやすく解説!

「返り点の付け方が分からない」「返り点はパズルみたいで使い方があやふや…」とのように、古文ではなく、返り点そのものに苦手意識を感じている方も多いのではないでしょうか。
返り点を覚えることで古文や歴史的な知識の習得も見込めるため、古典だけでなく日本史に関しての知見を深めることもできます。
練習問題を基に、返り点の使い方や特徴を解説していくので、この機会に漢文の苦手意識を克服しましょう。
・返り点を使った白文の書き下し方
・返り点の種類や役割
・返り点を付ける方法
【 目次 】
1.返り点とは漢文を日本語に読み替える為の記号
2.返り点の種類と役割
2-1.レ点
2-2.一、二点
2-3.レ点と一、二点の同時使用
2-4.上、中、下点
2-5.甲、乙点
3.返り点の付け方
3-1.白文の横に数字を振る
3-2.返り点をあてはめて書き下し文に直す
4.返り点の練習問題
4-1.問題
4-2.答え
5.まとめ
返り点とは漢文を日本語に読み替える為の記号
返り点とは「漢文を無理矢理並び替えて、日本語のように読むための記号」です。
漢文は昔の中国語なので、中国語の文法で書かれています。しかし昔の日本人は、「漢文を読むために中国語を勉強しよう!」ではなく、「並べ替えて日本語の文法に合わせてやろう!」と考えた結果、返り点が発明されました。
返り点の具体的な役割は、文中で「前後の文字をひっくり返して読みなさい」「この文字はいったん飛ばして、後から読みなさい」などの合図をする役割を持っています。
ここで、意外と忘れがちなポイントは「漢文は、基本的に上から下に読む」ということです。
上から下に読んでいって、その漢字に返り点がついていなければそのまま読み、ついていれば、その返り点に従って読み飛ばしたり、次の漢字に飛んだりして読みます。実際にどのような返り点があるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
返り点の種類と役割
高校の漢文で習う返り点は5種類存在します。ここでは、それぞれの役割を、種類別に見ていきましょう。
レ点
「レ点」とは、カタカナの「レ」のような形をした返り点のことです。
「レ点」がつくと、「レ点」に接している2つの漢字は下から上に読むという決まりがあります。したがって、3つ以上の漢字に連続して付いている場合も、「下から上に読むルール」が3文字に適用されるだけなので、右側の例文のように、「①レ②レ③」→「③②①」と、逆から読むだけで大丈夫です。
よく、「レ点の上下の漢字をひっくり返して読む」と言われますが、レ点が連続すると混乱してしまう可能性が高くなります。「レ点に接する漢字は下から上に読む」と覚えれば十分でしょう。
一、二点
「一、二点」の上にある漢字は、「一、二点」の漢数字に沿って順番に読むという決まりがあります。「一、二点」は「いちにてん」と読みます。
この返り点は、もとの文中で離れた場所にある漢字を、飛び飛びに下から読ませたいときに使われます。最高で、一、二、三、四と、四点くらいまで続くこともあります。
また、「一、二点」で行き着く場所が、ひとつの漢字ではなく、熟語の場合もあります(その場合の熟語はハイフン(-)で繋がっています)。
図のように、「一、二点」は熟語の最後の漢字ではなくて、最初の漢字に付くということに注意しましょう。
レ点と一、二点の同時使用
高校の漢文では、「レ点」と「一点」がひとつになった返り点が使われることがありますが、一+レ点はレ点が先と覚えておきましょう。
一瞬、どう読んだらいいのか分からなくなりそうですが、落ち着いてそれぞれのルールを思い出せば、簡単に読めます。
「レ点」のルールは、「接している2つの漢字を下から上に読みます。「一、二点」のルールは、「上にある漢字を、漢数字に沿って順番に読みます。
この2つのルールをどちらも満たすには、「レ点」の下の漢字→「レ点」の上の漢字=「一点」の付く漢字→「二点」の付く漢字という読み方しか無くなるのが分かるでしょうか。
上、中、下点
「上、中、下点」は、「一、二点」と同じように、「上、中、下点」の上の漢字を、「上→中→下」の順番に従って読むときに使われます。また、「中」をつかわず「上→下」のみで使われることも多いです。
文の中に、すでに「一、二点」が入っているけど、さらに「一、二点」のようなルールを追加したい。でもまた「一、二点」を使うと、どの順番で読むのか分からなくなってしまう…という場合に、「上、中、下点」が使われるというわけです。
数学の数式で例えるなら、「一、二点」と「上、中、下点」の関係は、小カッコ( )と中カッコ{ }の関係に近いです。もっと例えると、1つの文の中に、2つの異なるワープ通路が交差している感じです。
甲、乙点
「甲、乙点」も、「上、中、下点」や「一、二点」と同じように、その記号の上の漢字を、ある順番に従って読むときに使われます。
文の中にすでに「一、二点」も「上、中、下点」も入っているけど、さらに「一、二点」のようなルールを追加したいという場合や、その順番に従って読ませたい漢字がたくさんある場合に、「甲、乙点」が使われます。
というのも、「甲、乙」というのは昔の数え方で、「甲(こう)、乙(おつ)、丙(へい)、丁(てい)、戊(ぼ)」と続くため、漢字の数が多くても対応できるというわけです。
よく「甲乙つけがたい」という言葉を聞きますが、これは、「1番2番がつけがたい」=「優劣がつけがたい」という意味です。
返り点の付け方
入試で出題されることは比較的少ないですが、学校のテストなどでは、「以下の白文(中国語の原文)に返り点を付けなさい」という問題が出ることがあります。
ここでは、漢文に返り点を自分で付けるときの付け方について見ていきます。
白文の横に数字を振る
ほとんどの返り点の問題では、白文とともに、考えるヒントとなる書き下し文がセットで出題されます。※定期テストなどでは、書き下し文の部分は暗記して解くという場合もあります。
そこで、まずは書き下し文に沿って、それぞれの漢字をどのような順番で読むのか、白文の横に数字を振っていきます。
※上の図の「於」は、置き字のため、書き下し文には入っていません。置き字を復習したい方は、「▶️置き字とは?読み方の一覧や見分け方を分かりやすく解説!」をご覧ください。
数字を振っていくと、数字が上から下に並んでいない漢字があります。このような漢字に返り点を付けていきます。
返り点をあてはめて書き下し文に直す
ここで、さきほどの2.返り点の種類と役割で確認した、それぞれの返り点の役割から考えれば、次の図のように返り点を当てはめることができるはずです。
この図に沿って、返り点を付けると、下の図のようになります。
最後に、自分で返り点を付けた漢文を読んで、正しく書き下すことができれば、完成です。
返り点の練習問題
それでは、返り点を使った練習問題を解いていきましょう。問題を解く前に、書き下し文について復習したい方は、「▶️書き下し文とは?漢文の基本ルールを練習問題付きで解説!」をご覧ください。
問題
答え
まとめ
いかがだったでしょうか?返り点をマスターして、漢文を得意にしてくださいね!