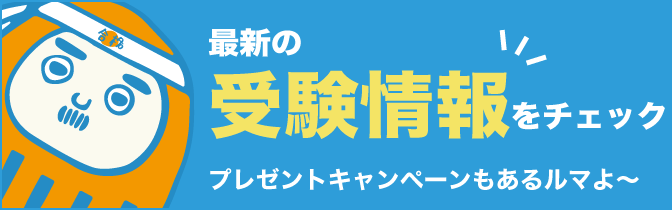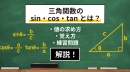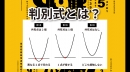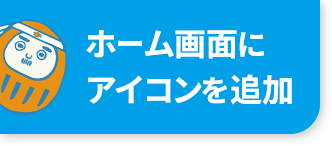書き下し文とは?漢文の基本ルールを練習問題付きで解説!

漢文の書き下し文は、高校の古典で漢文を習う際に基本となります。ひらがなに直す漢字には何があるか分からない、現代語訳や内容の理解が上手く出来ず困っている、などと疑問に思っている人も少なくないはず。
そこで今回は書き下し文について、基本ルールから例題までわかりやすく解説します。漢文を正確に書き下し文にできれば、現代語訳や内容の理解もかなりしやすくなるでしょう。
漢文を書き下し文にする際の基本知識やルール、練習問題も解説するので、書き下し文を勉強する際の参考にしてみてください。
1.そもそも「書き下し文」とは?
2.漢文を書き下し文にするときのルールは?
2-1.漢文の表記
2-2.基本的には、訓点に沿って書き下す
2-3.注意が必要な漢字
2-4.会話文の「と」にも注意!
3.書き下し文の練習問題
そもそも「書き下し文」とは?
書き下し文は「日本語文法の語順に並べ替えた漢文」です。日本語の文法の並び方に合わせて「書き下す」から書き下し文というんですね。
また、書き下し文は文語文法、つまり古文の授業で扱うような昔の日本語で、歴史的仮名遣いを用いて書かれます。なので、書き下し文にすれば、中国語である漢文が古い日本語である古文とほぼ同じように読めてしまう、というわけですね。
また、漢文の書き下し文と現代語訳が、どちらがどちらか分からなくなるという人がいます。これも、文語文法と歴史的仮名遣いで書かれている、古文のような文が漢文の書き下し文であり、それに対して現代語訳は、現代の文法と現代仮名遣いで書かれている、現代語に翻訳した文です。
現代語訳であれば、「なり」「べからず」などの文語の言い方は使いませんからね。
漢文を書き下し文にするときのルールは?
それでは実際に、どのように漢文を書き下し文にするのか見ていきましょう。
漢文の表記
漢文の問題では、ほとんどの場合原文である漢字だけの「白文」に「送りがな」「返り点」「句読点」の3つを加えた形で出題されます。この3つをまとめて「訓点」といいます。
さらに加えて、現代日本語と違う意味の漢字や、難しい漢字には、「振りがな」がつけられます。
基本的には訓点に沿って書き下す
漢文を書き下し文にする際には、基本的に、訓点に沿って上から書いていきます。
返り点を見て、漢字を読む順番を調べる
まずは、返り点を確認し、読むべき順番に漢字を並び替えます。このとき、句読点も1字として、漢字と同じ扱いで読む順番を確認してください。句読点によって意味が変わることもあるため、忘れずに書き写しましょう。
送り仮名を歴史的仮名遣いで書く
返り点の順番で漢字を見ていくと、漢字に送り仮名がついている場合があります。送り仮名は漢字とセットとして扱うため、その漢字のすぐ下に書きます。その際は、カタカナで書かれた送り仮名をひらがなに直し、歴史的仮名遣いのままで書くことに注意してください。
※「而」という字が消してありますが、これは以下の置き字の説明で解説します。
注意が必要な漢字
漢文から書き下し文にする際に、そのまま書き写してはいけない漢字がいくつか存在します。訓点に沿って書き下しているときに、以下のような漢字にぶつかったら、特殊な書き下し方をすると思い出してください。
無視すべき置き字一覧
漢文には「置き字」という文字があります。もともとは意味のある文字だったのですが、日本語に翻訳すると、なくても意味が通じてしまうことから、書き下し文にするときに消してしまうことになっています。なお、置き字についてもっと詳しく知りたい方は▶︎置き字について解説した記事をご覧ください。
主な置き字は以下の通りです。
日本語の助動詞・助詞にあたる文字は、ひらがなに直す
漢文はすべて漢字なので、当然、日本語の助動詞や助詞にあたる文字も漢字で表記されます。したがって、助詞や助動詞を表す漢字は、ひらがなに直して書きます。
しかし、注意が必要なのは、助詞や助動詞を表す漢字が別の意味として使われているときはひらがなにしないということです。その漢字が助詞や助動詞として使われているとき、つまり、助詞や助動詞の読み方で読むときにだけひらがなに変えて書きます。
なお、古文の助動詞の復習をしたい方は、▶︎古文の助動詞の意味を説明する記事をご覧ください。主な助動詞になる漢字は以下の通りです。
※()内のカタカナは送りがな
主な助詞になる漢字は以下の通りです。
※()内のカタカナは送りがな
これらの表にある読み方をするときは、ひらがなに直してください。
再読文字の2回目の読み方は、ひらがなに直す
再読文字の2回目の読み方もひらがなに直します。例えば、「未」ならば、「未だ~ず」と、1回目の読み方である「未だ」は漢字のまま、2回目の読み方の「ず」はひらがなに直して書きます。
これは、2回目の読み方が助詞・助動詞にあたるためです。主な再読文字は、▶︎センターによく出る漢文 再読文字の記事をご覧ください。
会話文の”と”にも注意!
会話文や引用文で「」を使うとき、訓読漢文(訓点は書き込まれているが、書き下されていない漢文)では、「」の中に‟と”が入っており、そのまま書くと「~~~。と」のような形になってしまいます。
しかし、日本語では引用の‟と”を「」の外に書くため、書き下し文および現代語訳では、「~~~。」と。または「~~~」と。の形に直します。
書き下し文の練習問題
それでは、最後に練習問題です。次の漢文を書き下し文にしてください。
(答え)
まとめ
いかがだったでしょうか?書き下し文をマスターして、漢文を得意にしましょう!