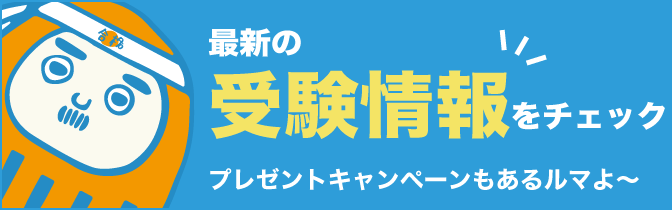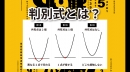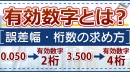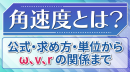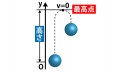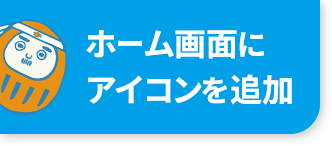熱力学第二法則とは?高校物理をわかりやすく解説

物理学で難しいイメージのある学問ですが、それに輪をかけているのが熱力学でしょう。
熱力学そのものは様々な分野に応用されるものであり、現代の科学技術を根幹から支えるものと言っても過言ではありません。
そんな熱力学の中でも特にわかりにくいのが、第二法則です。
ここでは物理が苦手な人でも、熱力学第二法則がわかるように解説をしていきましょう。
【PR】勉強を効率的に継続して、志望校に合格したい方必見!

↓無料ダウンロードはこちら↓
【目次】
1.そもそも熱力学第二法則ってなに?
熱力学第二法則は、端的にお伝えしますとエネルギーの移動の方向と、エネルギーの質に関する法則だと考えてください。
熱力学第一法則、いわゆるエネルギー保存の法則では、ΔU=Q+Wといった公式がありました。
熱力学第一法則について知りたい方はまとめた記事があるので下記のページを参考にしてみてください。
熱力学第一法則がイラストですぐわかる!練習問題付き
話を戻しましょう。しかし、熱力学第二法則ではそうしたものがありません。
経験則的に分かっていたことを、改めて定めたものだと考えられるからです。
まずはエネルギーの移動の方向について、解説をします。
熱力学を表現するには様々なものがあるのですが、その中でも代表的なものが3つあります。
それぞれに紹介をしていきましょう。
1-1.【熱力学第二法則①】クラジウスの原理とは?
最初に紹介するのはクラジウスの原理です。
内容は「高温の熱源から低温の熱源へと正の熱をうつす以外は、他にもどんな痕跡も残さないようにはできない」というものなります。
法則の定理のまま説明すると、首をひねってしまう人も多いでしょう。
そこでわかりやすく例を出してみます。
熱いものから冷たいものへ熱は自然に動いていきますが、その逆は何らかの仕事をしなければ起こらないというものです。
例えば、冬のお風呂を考えた時に、沸かしたお湯は外気と触れると、時間経過とともに温度が下がり、冷めてしまいます。
これはお湯から外気へと熱が移動したと言えるでしょう。
反対に、外気からお湯を作るには、熱を与えるという仕事をしなくてはいけません。
自然に温度の高いお湯になることはない、というのがクラジウスの原理の内容になります。
1-2.【熱力学第二法則②】ケルビンの原理とは?
ケルビンの原理、またはトムソンの原理とも呼ばれます。
どちらも同じ人なのですが、トムソン氏が学術的な功績をおさめたことで、ナイトの称号を得たのです。
そして、ケルビン卿と呼ばれるようになったので、呼び名が2つあるという形になってきます。
内容としては「ある熱源から熱を取りだしたとしても、それをすべて仕事に変えられない」というものです。
これは火力発電などを考えてみると、わかりやすいでしょう。
火力という熱を使って電気というエネルギーを取り出すのですが、その効率は良くても50%ほどしかありません。
蒸気機関などで、何かを動かすとしても100%最初のエネルギーは仕事として変換されないのです。
ちなみに、昨今話題になっている太陽光発電ですが、効率の良いものでも約20%ほどの発電効率しかありません。
つまり、得られたエネルギーの8割は、何らかの形で逃がしてしまっているのです。
この効率化を進めることができれば、より社会へのエネルギー供給が楽になるでしょう。
1-3.【熱力学第二法則③】オストワルドの原理とは?
では、最後にオストワルドの原理についても紹介します。
これはとてもわかりやすく「第2種永久機関は実現しない」という内容になっています。
第2種永久機関というのは、1つの熱源から正の熱を受け取って、すべて仕事にする以外に、なんの痕跡も残さない機関のことを意味します。
少しわかりにくくなってしまいました。
これを言い換えると、先ほどの蒸気機関のようなものです。
熱によって発生した蒸気のエネルギーを、100%仕事にするのは無理だと言っています。
ちなみに、この第2種永久機関は特許申請ができないそうです。
なぜなら実現したといって、申請する人が後を絶たなかったからだそうで、当時は随分と役人が迷惑したのでしょう。
既にお気づきかもしれませんが、クラジウスの原理、トムソンの原理、オストワルドの原理の3つは表現こそ違いますが、すべて同じことを言っています。
つまり、エネルギーの移動は高い方から低い方へと自然に起こるけれどその逆は起こらず、熱をすべて仕事に変換できないということです。
これが熱力学第二法則における、エネルギーの移動についての説明になります。
2.熱力学第二法則をさらに知ろう!エネルギーの質とは?(理工学系の大学を目指している人向け)
熱力学第二法則で言及されるのは、エネルギーの移動とエネルギーの質の2つです。
エネルギーの移動については、先にお伝えした通りになります。
では、もう1つのエネルギーの質について考えてみましょう。
ここで重要になるのが、エントロピーという言葉です。
一時期、小説や漫画、アニメなどのフィクションで良く用いられていましたので、ご存じの人も多いでしょう。
エントロピーとは、日本語にすると乱雑さ、無秩序、不確定性といったような意味になります。
どの意味をとるのかは、取り扱う分野によっても異なってくるのですが、一般的には乱雑さと覚えておくといいでしょう。
熱理学第二法則では、このエントロピーは断熱系において常に増大し続けるものである、と考えています。
断熱系とは、他と熱のやりとりができない遮断された熱力学系を意味します。
つまり、閉じた空間であると思ってください。
熱エネルギーは、100%仕事に変換することができません。
ただ、効率の良い仕事を得ることはできます。
これをエネルギーの質とすると、エントロピーとは質を下げる要素であると考えられるのです。
そして、エントロピーは常に増大していくとされますので、最終的にすべてのエネルギーは仕事ができなくなります。
これが熱的死と呼ばれるものです。
ただ、こうした説明もわかりにくいでしょうから、いくつか例を出してわかりやすく解説をしていきます。
エネルギーの質とエントロピーの関係性
ここに2つの図書館があると想像してください。
2つの図書館ともに、同じ本が蔵書されています。
一方の図書館は司書がいて整然と本が整理されていますが、対するもう一方の図書館は、整理整頓されていないとしましょう。
同じだけの本が蔵書されていますので、熱的な量で見れば同じエネルギーを持っていると考えられます。
しかし、図書館を使う方からすればどうでしょうか。
整理整頓された図書館は使いやすいですが、されていない方はどこにどんな本があるかわかりません。
この図書館の乱雑さこそが、エントロピーという概念です。
整理整頓された方はエントロピーが低く、エネルギーの質がいいとなります。
反対に整理されていない図書館はエントロピーが高く、エネルギーの質が悪いとなるのです。
整頓された方の図書館についてですが、いくら司書が整理すると言っても徐々に図書館の整理は崩れていきます。これがエントロピーの増大則にあたるものです。
まとめ
以上が、熱力学第二法則になります。
エネルギーの移動と質の2つをしっかりと押さえておきましょう。
理系学部に進むと、より詳しい計算式を伴った理論を習います。
概念としては難しいものですが、言い換えてみるとそこまで難しいものではありませんので、しっかり自分の中で消化するようにしてください。